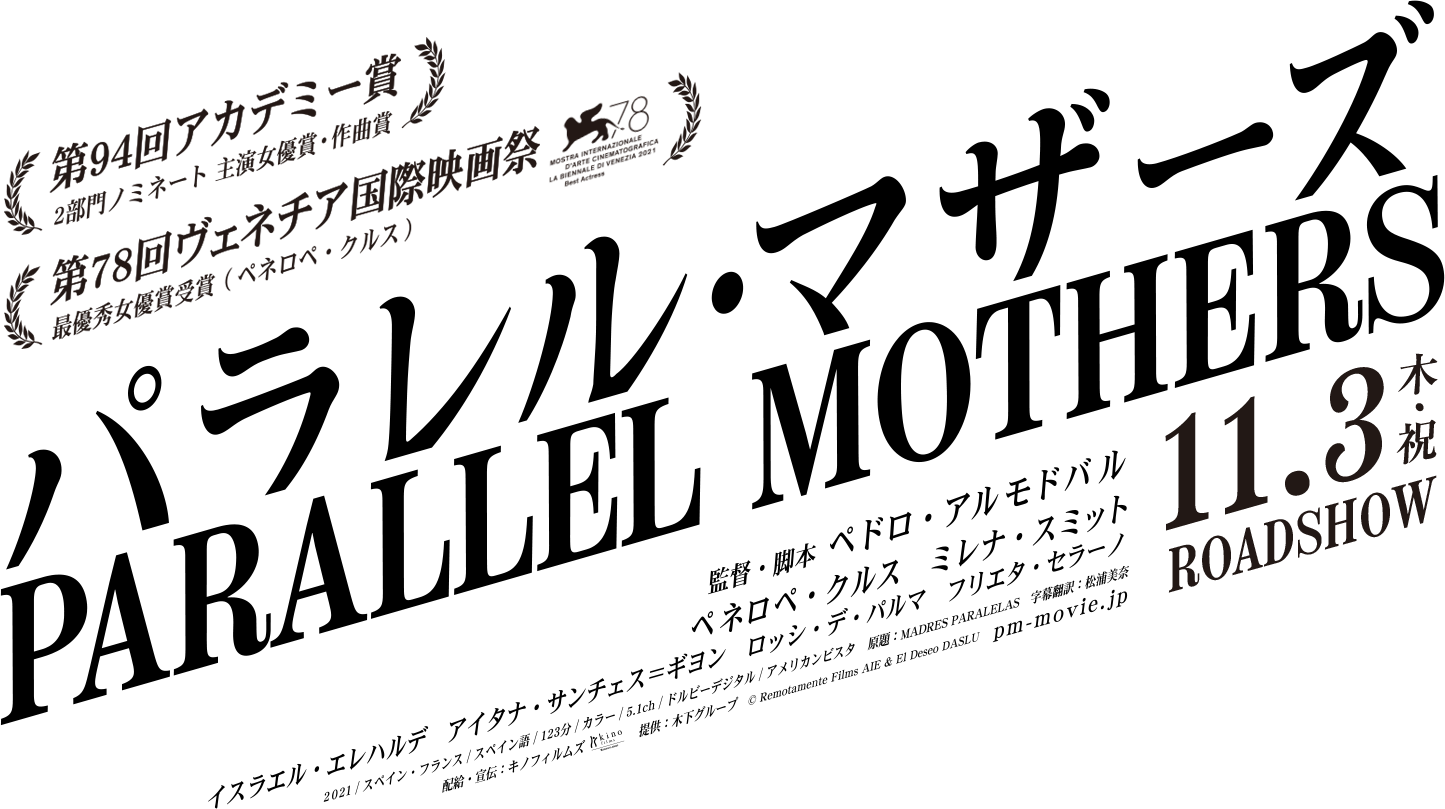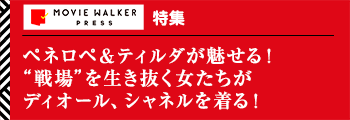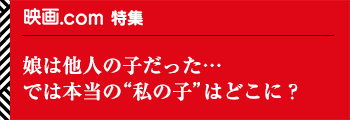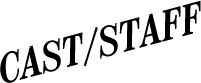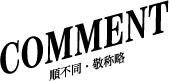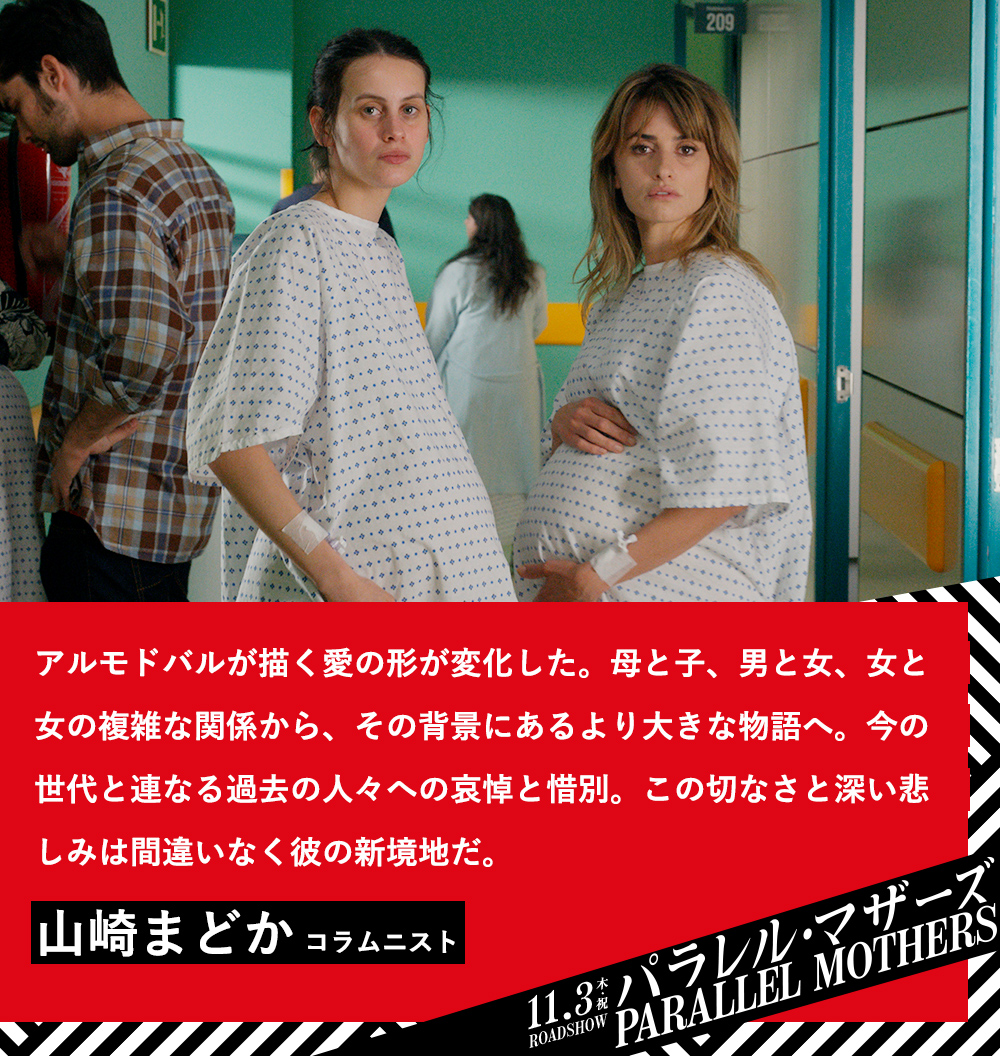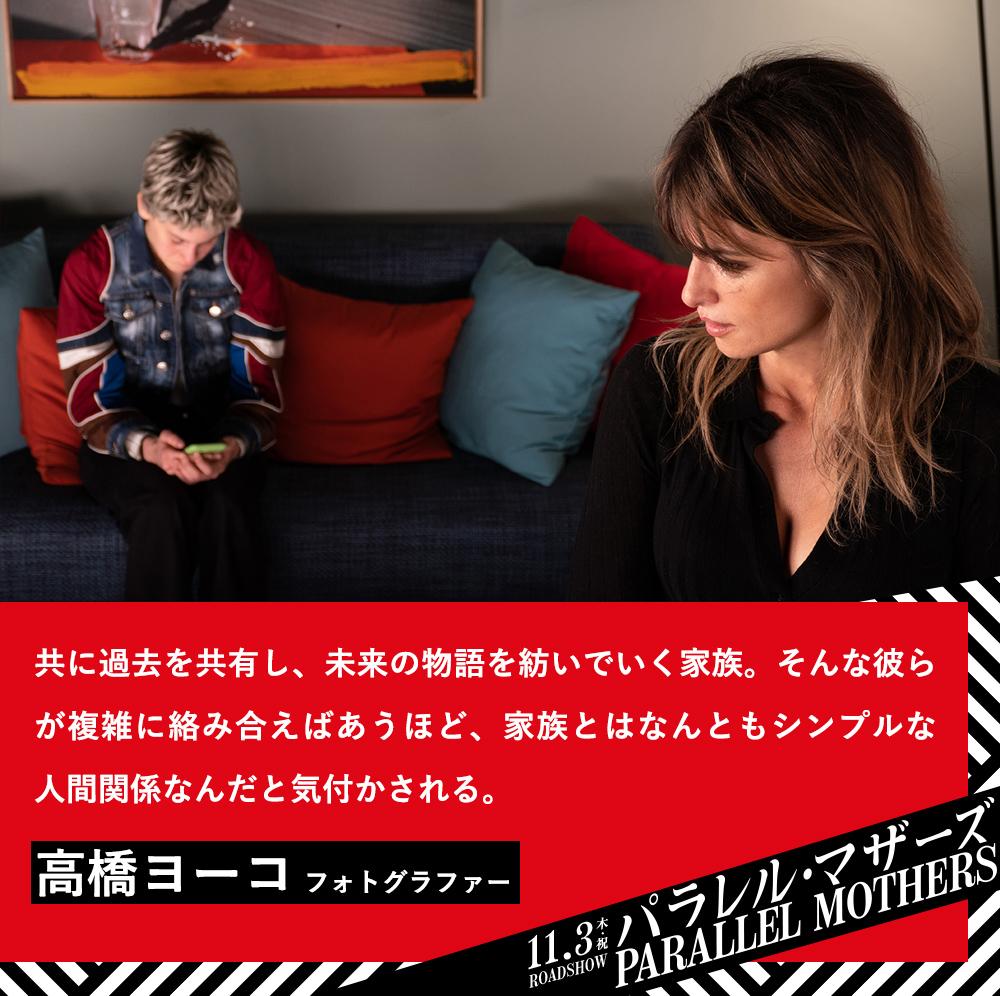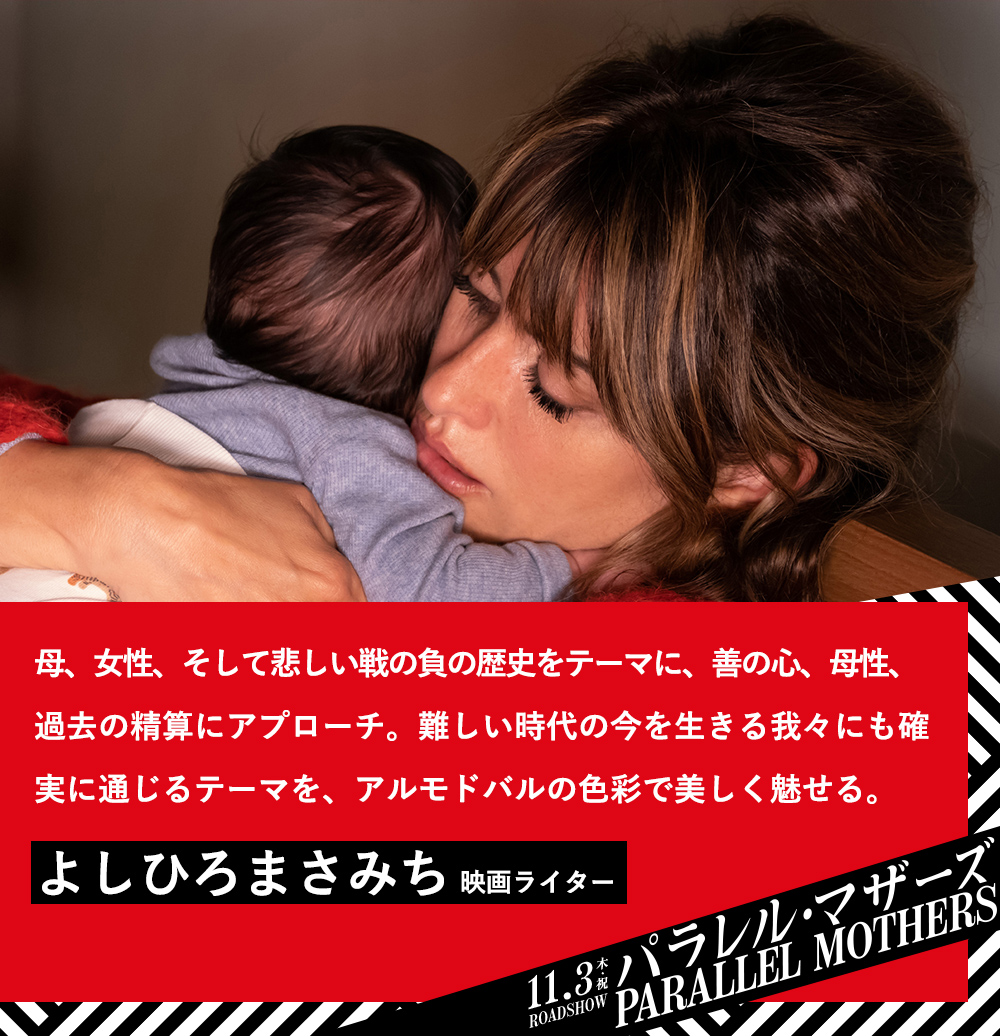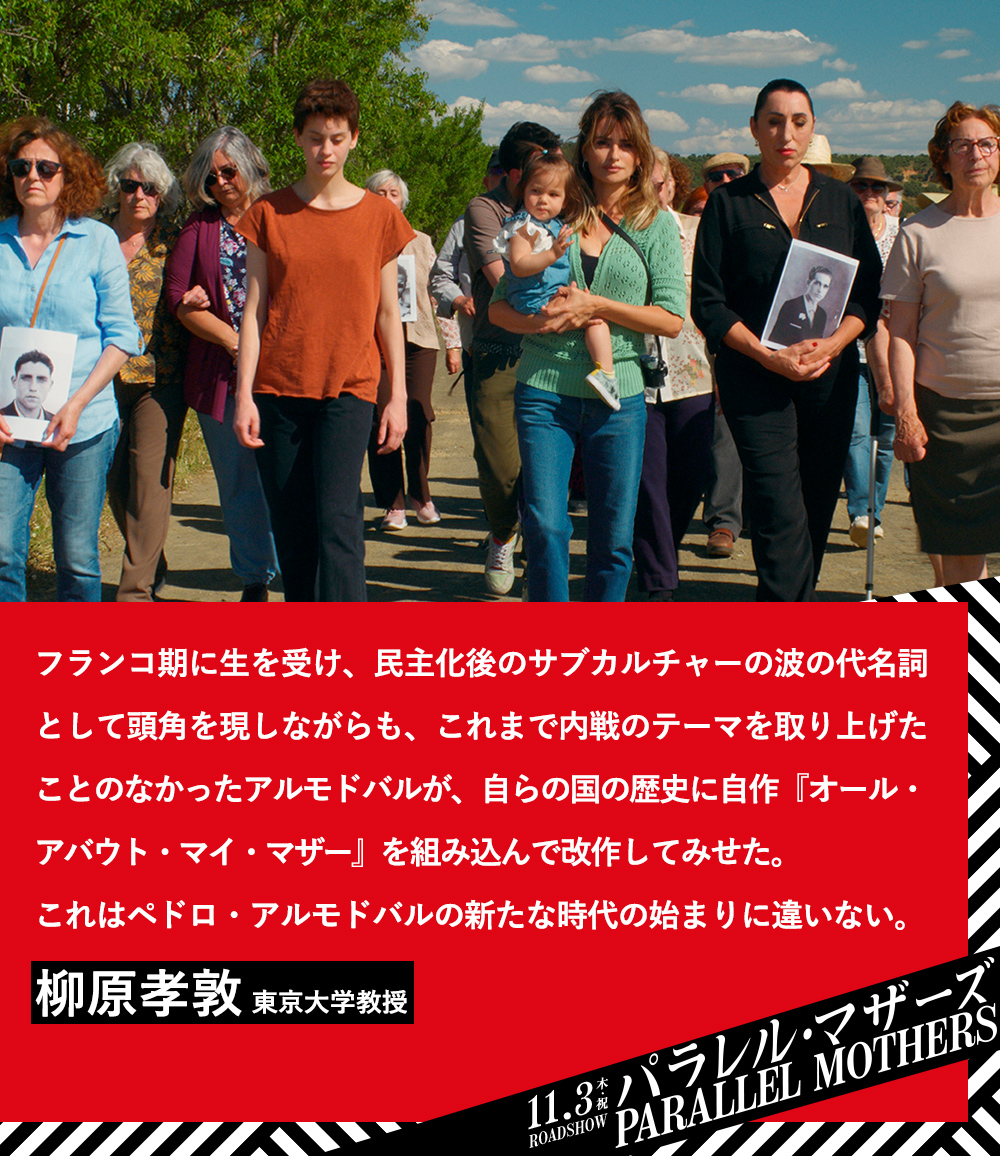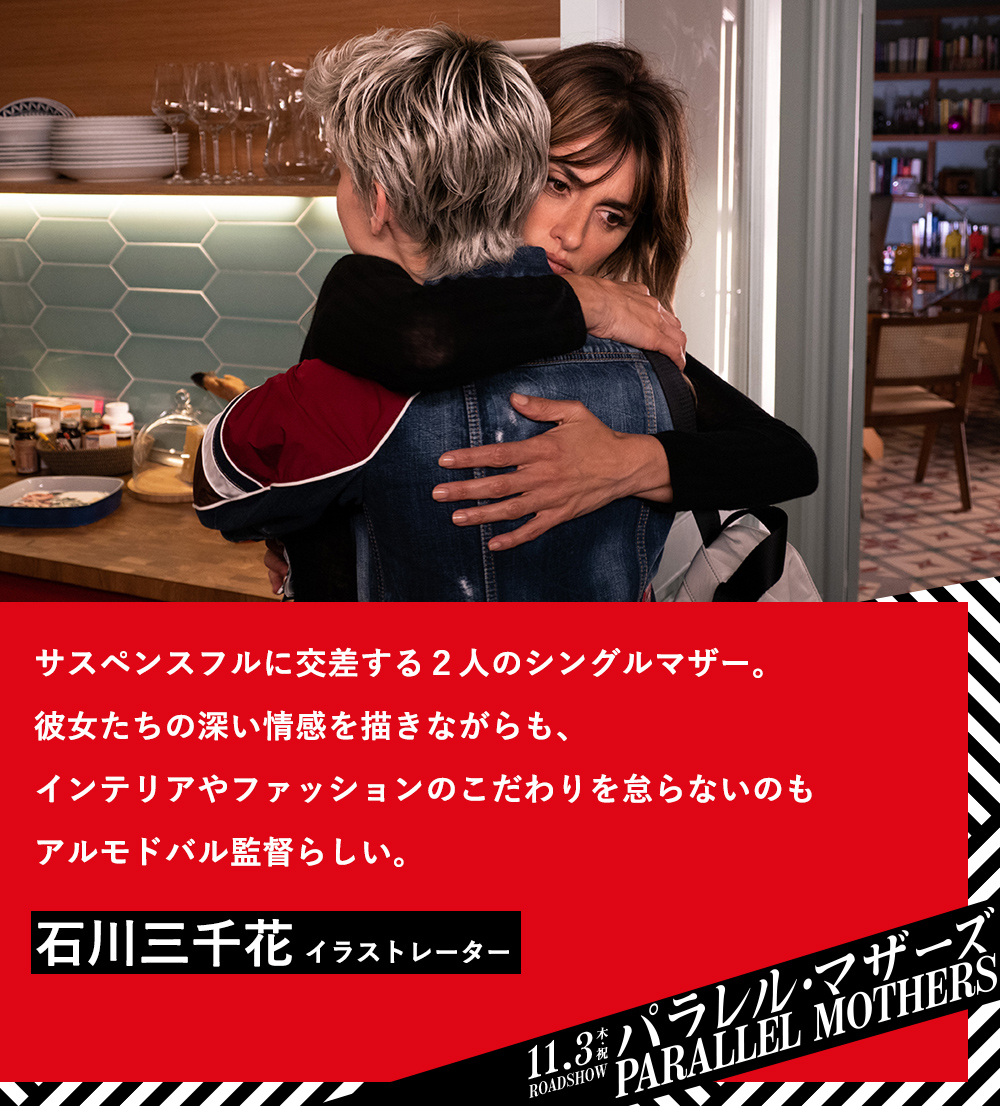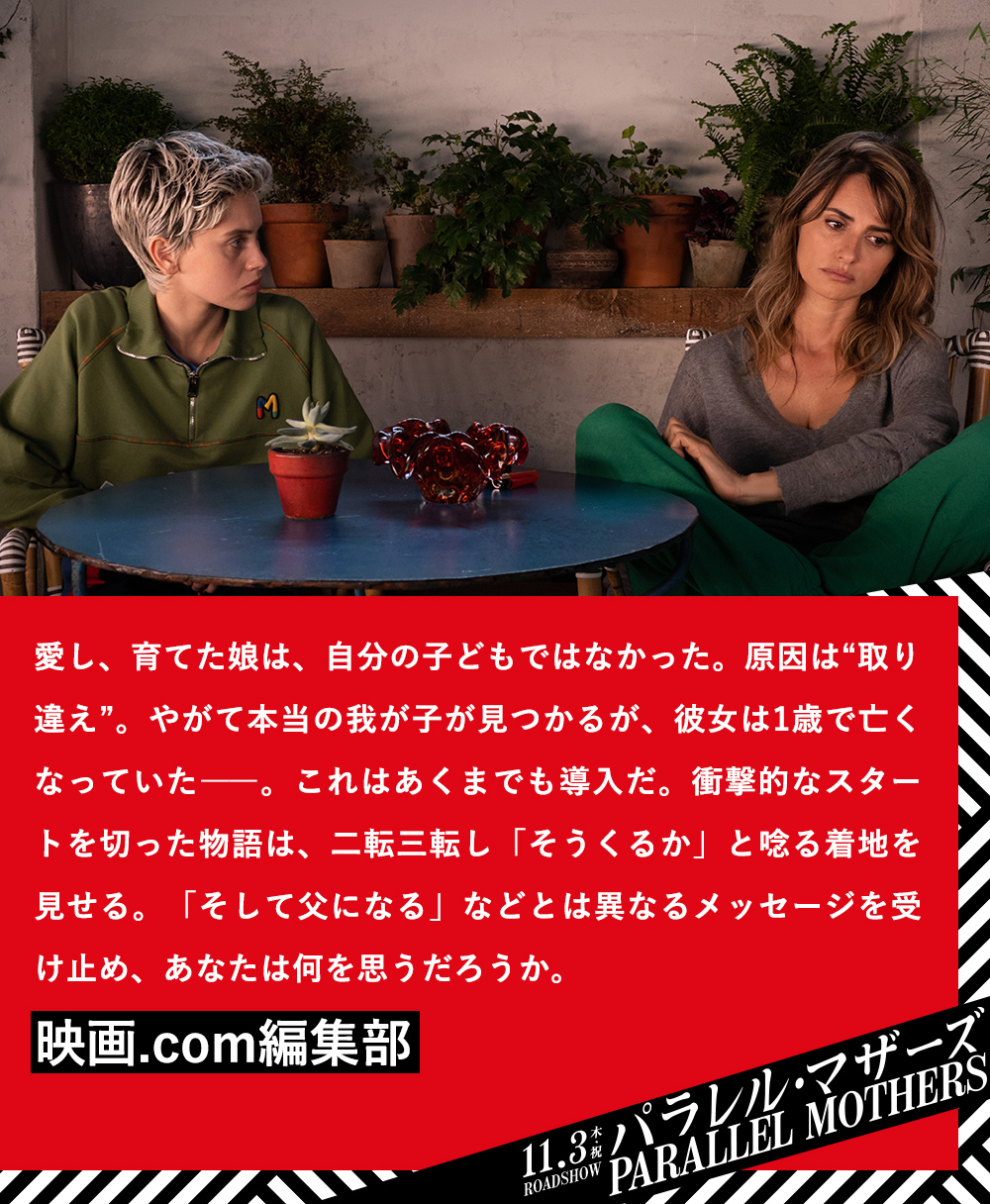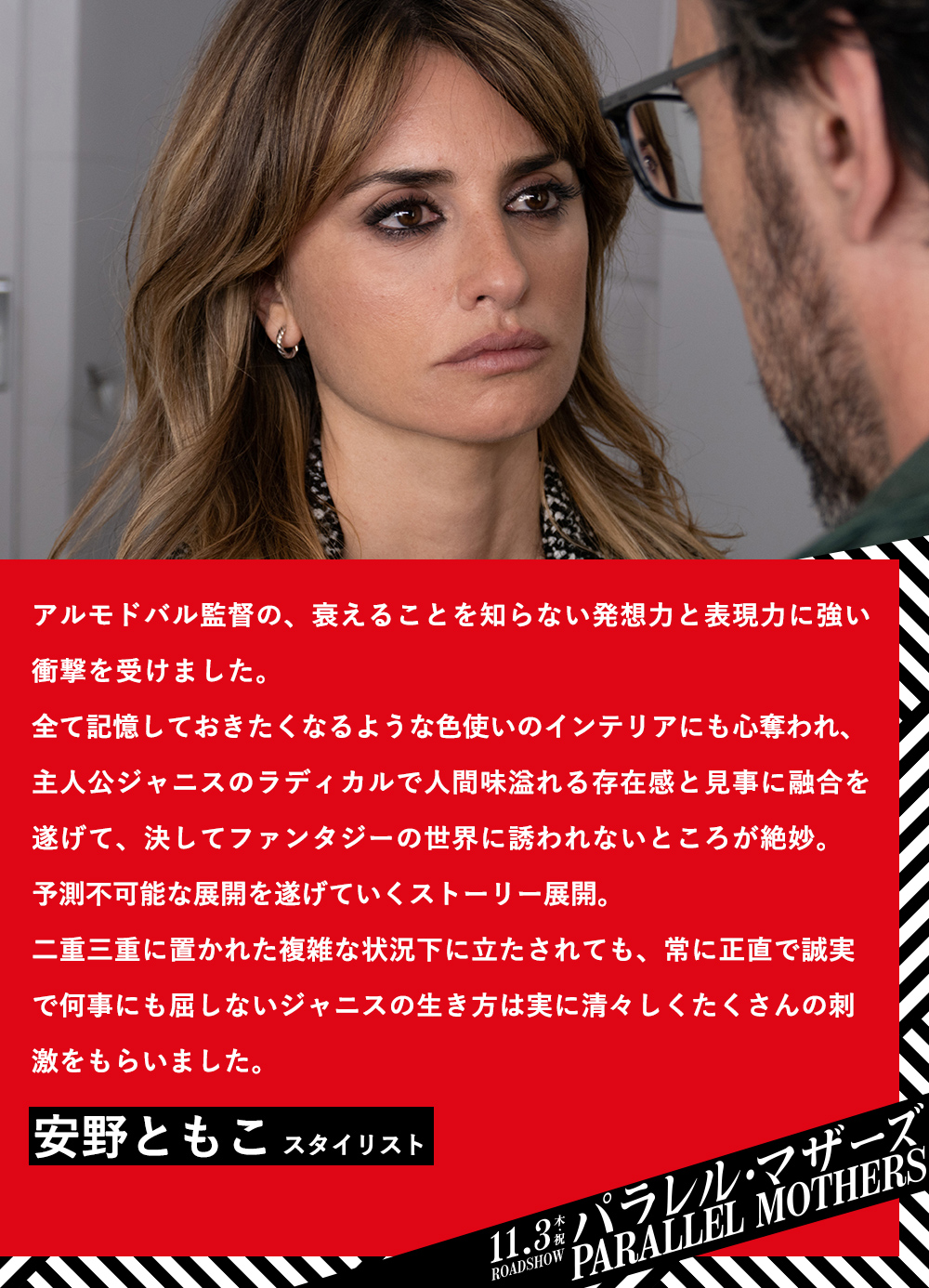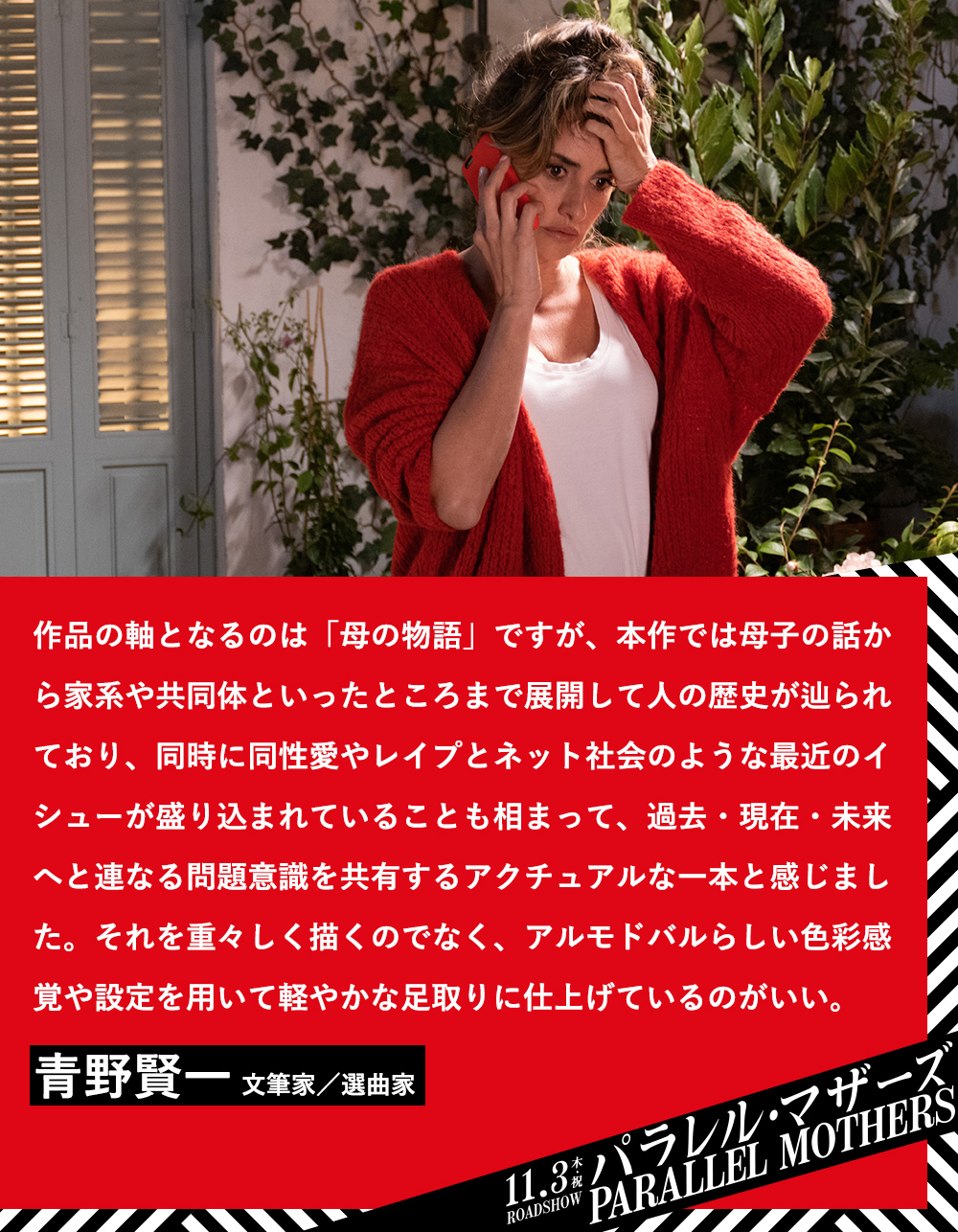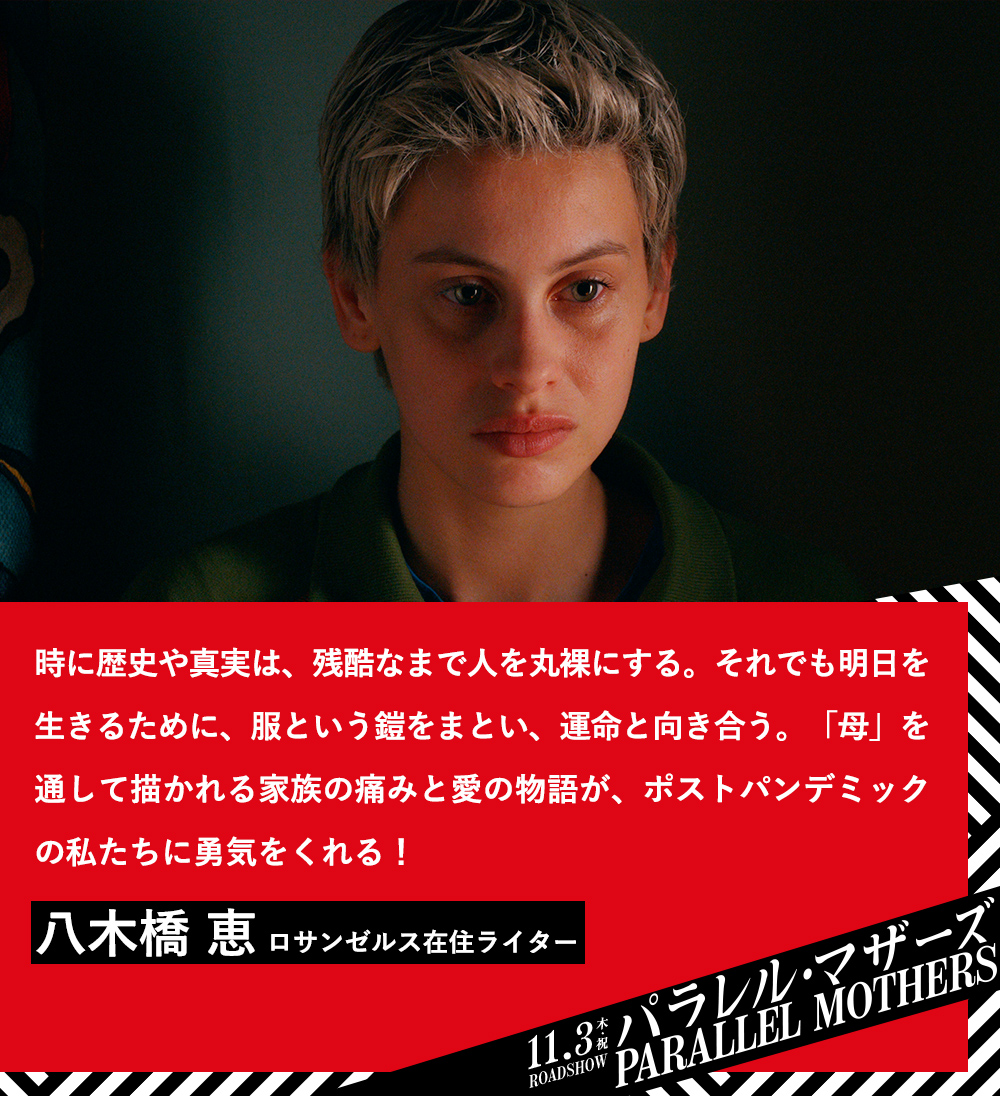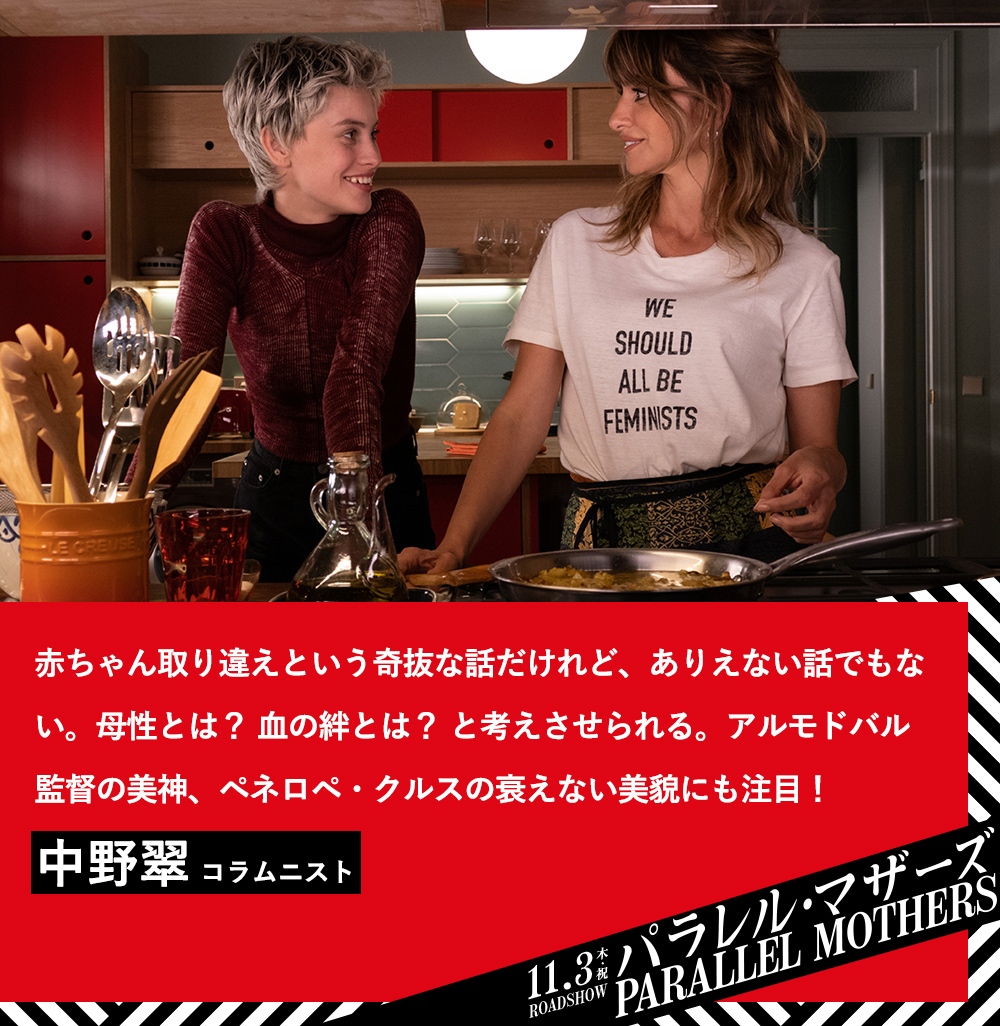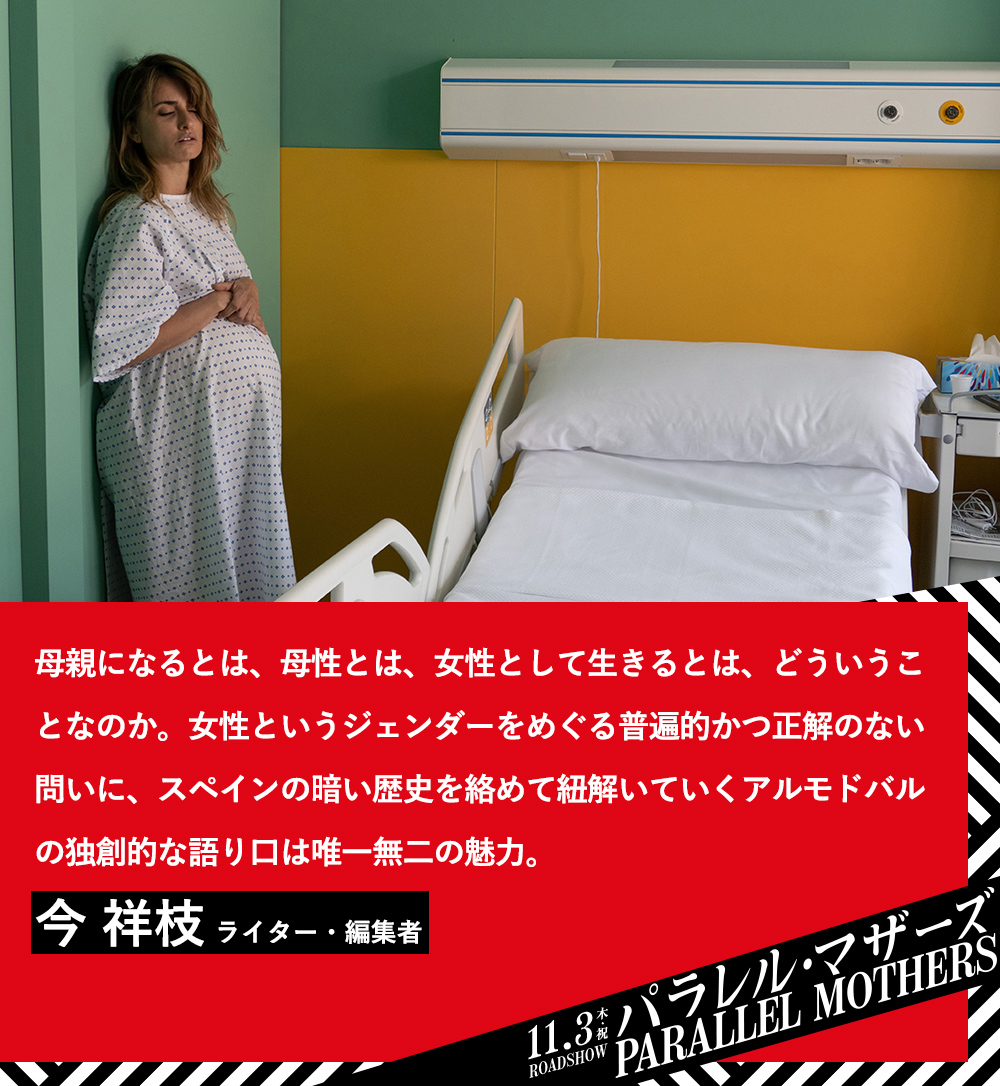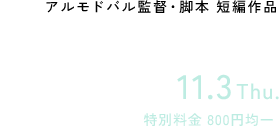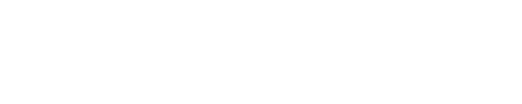INTERVIEW with Pedro Almodóvar
原作であるコクトーの戯曲は、私にとって古くから馴染みがあり、これまでにも時折、私の他の作品にインスピレーションを与えてきた。『神経衰弱ぎりぎりの女たち』の脚本を書き始めたときに映画化も考えたが、結果的にできたものは、恋人からの電話が来ないというシナリオのとっぴな喜劇で、電話のモノローグを入れるような場所はなかった。その1年前には、『欲望の法則』 の一場面に入れた。その場面は、ある映画監督が、本作の脚色作品の1つで、出演している妹に演出を施すというものだった。その時に、主人公の神経があまりにもダメージを受けたために、自分を捨てた男と一緒に暮らしていた家を斧でめちゃくちゃにするという設定を思いついた。斧を使うというアイデアは、『欲望の法則』で思いつき、今回、登場させたというわけだ。
私は、コクトーの戯曲をできるだけ原作に忠実に脚色しようと再び机の前に座り、何十年かぶりに原作を読んだ。だが「忠実」ということ自体が私の性分ではないため、本作は、原作に「大まかに基づいている」という説明を加えている。確かにそうだからだ。女の苦悩や、欲望の法則の高い代償という本質は原作そのままにした(女には、たとえ命と引き換えても、その欲望の法則がもたらす高い代償を支払う覚悟がある)。また、主人を待ち焦がれる犬と、思い出の詰まったスーツケースも登場する。電話での会話、待っている間とその後に起こることなどそれ以外のものは、私自身の現代女性の理解に基づいて脚色した。スーツケースを取りに来るというだけの電話をするのにも何日もかけるような男を狂気に至るまで愛しているが、媚びるほど依存しきってはいないというような女性だ。彼女は、原作に登場する女性のように従順ではない。私たちの生きている時代を考慮したら、それはあり得ないのだ。
私は常にこの脚色を実験とみなしてきた。それは一つの思いつきであり、演劇においては「第四の壁」と呼ばれ、映画においては本物そっくりなセットの壁を支える木組みの裏側にあたる部分を、あらわにするというアイデアだ。この木組みは、いわばフィクショナルなものが持つ物質的なリアリティなのだ。
この女の現実は、痛みであり、孤独であり、生活の中で彼女を取り囲む闇である。私は、主人公の家が、映画撮影用のサウンドステージの中に組み立てられている物であると早い段階で示し、ティルダ・スウィントンの抜群の演技を通して、これらを全てあからさまで、胸を打ち、そして説得力のあるものにしようと努めた。また、映画的なものと舞台的なものの様子を混ぜ合わせた。例えば、彼女が恋人を待ちながらベランダに立って街を眺めている場面では、観客の目には、(スタジオの)壁しか見えず、その壁には他の撮影からの印がまだ残っている。スカイラインも、街の風景もないのだ。彼女の目に入るのは、ただ何もない殺伐とした闇の空間だけ。そうすることで、主人公の孤独感と彼女の暮らす闇を強調することができた。このように、撮影を行なったスタジオが、全ての演技の舞台となった。
英語を使用することも、私にとっては実験であった。私は、仕事をするときは完全に自由奔放になる映画監督だが、今回は、標準的な形式ではなかったため、さらに自由を感じた。自分の言語、90分という最低限の時間、セットの装置の背後にあるものを見せないように注意しなければいけないといった制限がないことは、非常に解放的だった。
かといって、全てがすんなりと噛み合ったわけではない。私の頭の中には、がんとして動かない制限が存在した。そのように自由に作られた作品も、他の作品以上に演出に厳密さを要するのだ。現実的でないもので私が見せたものは全て、主人公が孤独と疎外を体験しているということを強調することが目的だった。彼女が隔離されて生きていることを表現したかったのだ。突飛な表現の裏には、必ずドラマチックな概念が存在する。頭上からのショットでセット全体が映るとき、人形の家のような狭い空間に閉じ込められた主人公を見せたかったのだ。
冒頭のクレジットの前の部分の言葉は、オペラのプロローグを思わせる。バレンシアガの服のおかげで、そういった幻想を作り出すことに成功した。最初のシークエンスでは、高級服をきた女が待っている。彼女はまるで、物置に取り残されたマネキンのように見える。
実を言うと、私はこの実験を十分に楽しんだ。例えば、通常は非常に醜い合成用の巨大なグリーンスクリーンを、オペラの緞帳のような物に変えることは、刺激的で、楽しく、心がわくわくした。この映画に対して、室内劇で実験的な作品に対するようなアプローチをとったことで、家具、小道具、そして音楽に対する些細な偏見を忘れることができた。いくつかの家具は、私の他の映画作品にも登場したものだ。音楽でも同じことが起こった。私は、アルベルト・イグレシアスに、これまで一緒に手がけた映画作品の曲を、本作のテンポと雰囲気に合ったものに編曲するように依頼した。そして彼はまさにそれを成し遂げてくれた。いくつかの電子音楽ベースの曲を除いては、『抱擁のかけら』、『バッド・エデュケーション』、『トーク・トゥー・ハー』、『アイム・ソー・エキサイテッド!』の曲を編曲したものだ。
制作を開始する前に、すでに美学に関して多くのアイデアが浮かんでいたが、この作品はそもそも、言葉と1人の女優を中心に展開する。その言葉を私なりに脚色することは困難であったが、私の言葉に真実味と感情を持たせる優秀な女優が必要だった。(全てがより分かりやすく、自然主義的な)コクトーの作品に比べて、私の作品はより抽象的であったため、演じるのはより困難だった。それは、現実的な支えがほとんどない状態で、技巧で固められることで実現した。一貫性のあるのは女優の声のみで、観客が突然の衝撃を受けずに物語を追っていくための唯一の手引きとなる。今回ほど、真に才能のある女優を必要としたことはなかった。そして、私が夢見た特徴の全てを持った女優を見つけた。ティルダ・スウィントンだ。
本作の言語は英語で、私にとって初の英語作品である。撮影は実にのどかであったものの、英語の作品に再び挑戦する自信はない。ただ、ティルダ・スウィントンが母国語で演技をする作品を監督することは可能だと言うことは確信している。最初から最後まで彼女だけが演技をするこの短編映画は、彼女の才能の幅の広さを証明している。彼女の知性と意欲のおかげで、私の仕事ははるかにやりやすくなった。特に、彼女のとてつもない才能と、私に対する絶対的な信頼も、大きな役割を果たした。全ての映画監督がこのような気持ちになれることを夢見る。また、このような映画を制作できたこと自体が、成長の糧となる。
照明は、再びホセ・ルイス・アルカイネに任せた。彼は、スペイン映画界に残された最後の光の巨匠である。ビクトル・エリセ監督の傑作映画 『エル・スール』で活躍した伝説の撮影監督だ。多くの作品を一緒に手がけてきたアルカイネは、私の好みの彩度と鮮やかな色、そして私がテクニカラーに対して郷愁を抱いていることを、誰よりも理解しているのだ。
また、フアン・ガッティがクレジットとポスターのデザインを担当。私の家族とも言える制作会社エル・デセオの仲間たちが、ティルダ・スウィントンと共に、全てを引っ張っていってくれた。私たちが楽しんだのと同じくらい、皆さんもこの映画を楽しんでくださることを期待する。